
UTSUWA探訪~奈良家編~
202010/27
- カテゴリー

202010/27
2019年の記事になりますが、
奈良を訪れる方におすすめするお店などをご紹介しております。
現在のお店の状況その他が変更になっている場合がございますので、
訪れる前にお調べいただくことをお勧めします。
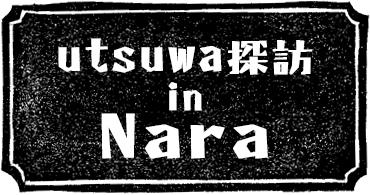
からの続きになります🚃
近鉄新庄駅から近鉄奈良駅に
向かう特急電車の中で、
奈良県名物「柿の葉寿司」を😋ペロリ


近鉄奈良駅で購入しておいた
中谷本舗さんの ゐざさ 柿の葉寿司
数ある柿の葉寿司の中でも、
特に中谷本舗さんの柿の葉寿司が
大のお気に入りなのです💛
奈良に来たら食べないとねー♪
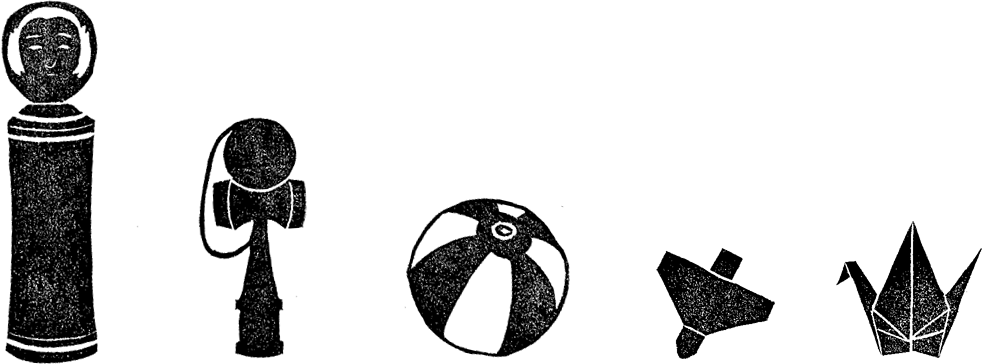
さて、今回のutsuwa探訪は、
近鉄奈良駅ちかくの「ならまち」を
中心に回る予定✨
その前に✋
奈良駅からほど近い「興福寺」へ

この日は平日だったため、
比較的人出が少なく、ゆっくり
見学ができました。
約300年ぶりに中金堂が落慶✨

新たに金箔を貼りなおした
釈迦如来像、薬王・薬上菩薩像(重文)、
四天王像を見ることができました。
まじかで見る王像は迫力満点!
そして、心洗われ背筋が伸びる
ような気持になるから不思議です✨
そして、五重塔に鹿

興福寺と言えばこの図ですね(*^^*)
京都とはまた違う、
奈良ならではの、静かな中にも
凛とした空気が素敵でした。
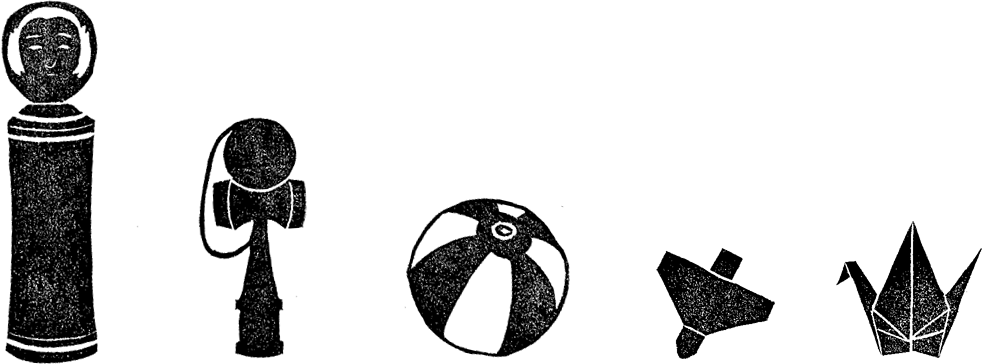
その他の神舎仏閣もゆっくり回りたい
所なのですが、、、
今回は1泊で来ているのでうかうか
していられません💦
器探しに「ならまち」へ向かいます♪
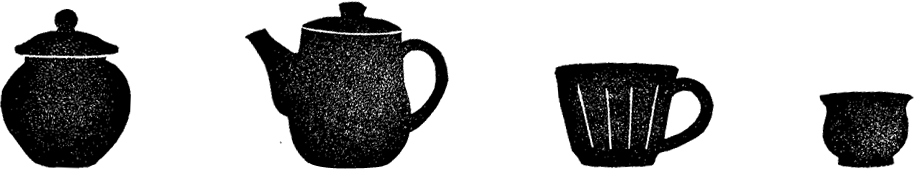
まずは、

創業300年の「中川政七商店」さんへ

近鉄 奈良駅から程近い
「ならまち」にある、
遊 中川 本店さんに伺いました。

伝統と現在のデザインの融合が
美しい品が沢山✨

包装紙のこだわりも一目瞭然です!
中川政七商店さんの始まりは、
1716年、奈良晒(ナラザラシ)の
商いを始めたのが始まりとのこと。
奈良晒【ナラザラシ】とは、
奈良地方で生産されてきた麻織物で、
天日晒されたものをいうそうです。
300年受け継がれてきた伝統が、
現在は色鮮やかなふきんとなり
陳列されてました。

デザインは勿論、機能も抜群!
新品はパリッとしていますが、
2、3度洗うとふんわりとして、
吸収も抜群!長持ちする点も
気に入っています。
友人へのお土産にも最適!
器好きの方へのお土産なら
きっと喜ばれますよ(^▽^)/
店内の奥にはカフェスペースも

茶論 奈良町店
何やら良い雰囲気ですね😍
そして、その先を抜けると、、


布蔵を改築して作られたという
ギャラリースペース✨時蔵
ひんやりとして凛とした空間


中川政七商店さんのロゴマークに
使われている鹿の陶器も圧巻です!
壁面には一面に布を収めるような
サイズの引き出しがびっちり!


布を保存するためではなく、
書類等を保存するために使用する
ための引き出しのようです。
金のタグには年号が入れあります。
2019年よりもずーっと先の
年号まで設計されていて、
この先も中川政七商店を
受け継いでいくという決意の
表れなのだそうです✨
さすが!老舗は違いますね。
美しい器と店内を楽しめた
楽しい時間でした( *´艸`)
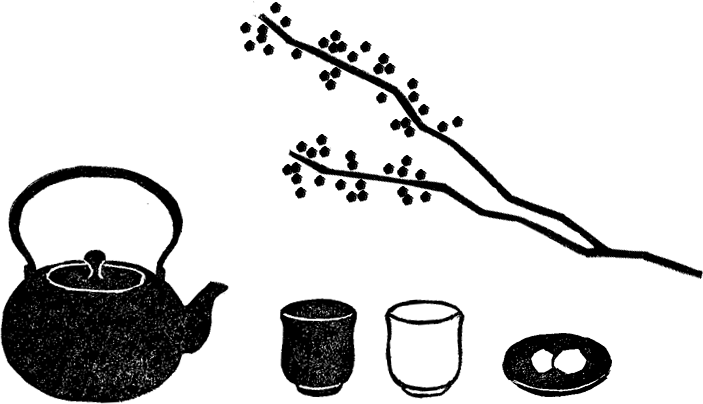
さてさて、お次は、
近鉄 奈良駅の2番出口から
ひたすらまっすぐ歩いて約15分の
ならまちの鳴川町にある
店内に入る前から
「ここには好きな器があるそう💛」の予感
中には、器、生活道具、アンティーク、
紙モノ等がショーケースやテーブル
に並べられ✨優しい空気が漂う店内


どの器も、料理をのせた図が浮かぶ
ぜひ使いたいと思わせる器ばかり✨

手に取る器どれも気に入ってしまう💦
悩むー( *´艸`)
その中で、これに決めた!と購入したのは
こちら

京都で制作している大井寛史さんの器
アンティークホウロウのように見える
パールシリーズのオーバルプレート。
半磁器の器なので取り扱いやすいのも
決定した理由のひとつです✨
輪切りオレンジを盛り付けたり、
サラダ、オードブル、サーモンのグリル
などなど盛り付けたい料理が
どんどん浮かびます(*^^*)
また来たい!そう思わせてくれた
素敵なお店でした♡
さぁー次どこ行こうかな♪
その前に、ここでひと休憩
先ほど散策していた時に見つけた
和菓子店でティータイム
いただいた上生菓子は、

目にも鮮やかな上生菓子
『南無観椿』

奈良町のシンボルである身代わり
猿を上生菓子で表現した
『庚申さん』
上品甘さとなめらかな口当たりが
至福のひと時✨
大正2年創業の歴史を感じる店内は、
落ち着いた雰囲気の中、お庭を眺め
ながらゆっくりと和菓子を頂ける
大人な雰囲気✨
生菓子と一緒にいただいたお茶の
お湯を入れた器も素敵✨

こういう器も欲しいなーと
またここでも器病が(*’▽’)💦
ギャラリースペースに並べられた
器も素敵でした✨

歩き疲れた足も軽くなり
器探訪再開です!

続きは次号で(^_-)-☆